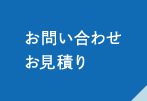ジャージャージャン!
トヨタ2000GT
すげー、
何がすごいかと言うと、
詳しくは、ウィキペデアで確認宜しく!
ジャージャージャン!
トヨタ2000GT
すげー、
何がすごいかと言うと、
詳しくは、ウィキペデアで確認宜しく!
トヨタ・2000GT
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索
| トヨタ・2000GT MF10型 | |
|---|---|
|
前期型
前期型リア
|
|
| 販売期間 | 1967年 – 1970年 |
| 設計統括 | 河野二郎 |
| デザイン | 野崎喩 |
| 乗車定員 | 2名 |
| ボディタイプ | 2ドアクーペ |
| エンジン | 3M型直列6気筒 DOHC(150ps/6600rpm 18.0kgm/5000rpm グロス値) |
| 変速機 | 2000GT専用5速MT(他に3速ATの設定あり) |
| 駆動方式 | FR |
| サスペンション | 4輪ダブルウィッシュボーン(コイルスプリング) |
| 全長 | 4175mm |
| 全幅 | 1600mm |
| 全高 | 1160mm |
| ホイールベース | 2330mm |
| 車両重量 | 1120kg |
| -自動車のスペック表- | |
開発までの経緯 [編集]
開発時の状況 [編集]
1960年代前半の日本におけるモータリゼーション勃興期、トヨタ自動車にとって最大の競合メーカーである日産自動車はフェアレディ、また四輪車メーカーとしては新興の本田技研工業はSシリーズをそれぞれ市場に送り出し、いずれも軽快なオープンボディのスポーツカーとして日本国内外で人気を集めた。これらのスポーツカーは自動車レースなどでもメーカーの技術力をアピールし、メーカーのイメージアップに大きく貢献する存在であった。 一方のトヨタ自動車は、日産自動車と並んで日本を代表する最大手自動車メーカーでありながら、1960年代前半にはスポーツカーを生産していない状態だった。社外の企業である久野自動車により、クラウンのシャーシを利用して浜素紀のデザインした個性的な4座オープンボディを架装したスペシャリティ・モデルの試作などは行われていたが、そのシャーシやエンジンなどはスポーツカーと呼ぶには非常に未熟なもので世に出ることはなく、自社のイメージリーダーとなるようなスポーツモデルが存在していなかった。 トヨタ自動車のスポーツカーには、1962年から大衆車パブリカのコンポーネンツを用いて系列会社の関東自動車工業で試作を進めていた「パブリカ・スポーツ」があり、1962年以降の原型デザイン公開を経て、トヨタ・スポーツ800の名で1965年から市販された。しかしこれは1000cc未満のミニ・スポーツカーであり、2000cc超の乗用車を生産する自動車メーカーであるトヨタのイメージリーダーとしては格が不足していた。 このため、輸出市場やレースフィールドで通用する性能を持った、より大型の本格的なスポーツカー開発が考えられるようになったのである。開発は1964年9月から開始され、シャーシやスタイリングの基本設計はトヨタ自社によって短期間で進められている。ヤマハ発動機の技術供与 [編集]
同時期、オートバイメーカーとしてすでに日本を代表する存在となっていたヤマハ発動機では、日産自動車と提携してクローズド・ボディの高性能スポーツカーの開発を進めていた[1]。日産との協力で開発コード「A550X」と呼ばれる試作車[2]も作られたが、この計画は日産側の事情により、1964年に開発途中で頓挫した。 そこでヤマハでは、スポーツカー開発のあらたなパートナーとして、トヨタ自動車工業にアプローチした。すでにスポーツカー開発に着手していたトヨタ側もこれに応諾し、プロジェクトリーダーの河野二郎、デザイン担当の野崎喩、エンジン担当の高木英匡、シャシーと全体レイアウト担当の山崎進一の4人を中心に1964年末から共同開発が開始された。この際、同年12月末にはトヨタ側の開発メンバーがヤマハに赴き、A550X試作車を実見している。 翌1965年1月より、トヨタ側の開発陣、河野、野崎、高木、山崎の4名がヤマハ発動機に出向き、2000GTの開発プロジェクトを推進していった。開発の本拠をヤマハ発動機に移すことになったのは、「本社は一切タッチせず。プロジェクトは(前出の)4名とヤマハ発動機でまとめること」という異例中の異例の方針をトヨタが打ち出したためである。開発プロジェクトは順調に進み、4月末に最終設計図が完成。計画開始からわずか11か月後の8月に試作車の第1号車が完成し、トヨタ自動車に送られたのである。 当時のトヨタは実用車主力のメーカーで、高性能エンジン開発や高級GTカーの内装デザインなどには通暁しておらず、2000GTの高性能エンジンや良質な内装には、ヤマハ発動機のエンジン開発技術や日本楽器の木工技術が大いに役立てられている。 ヤマハ発動機は戦時中に航空機用の可変ピッチプロペラの装置を製造していた技術・設備を活用するため、1950年代中期からモーターサイクル業界に参入して成功、高性能エンジン開発では10年近い技術蓄積を重ねていた。また1950年代後半以降のモーターサイクル業界では、四輪車に先駆けてSOHC・DOHC弁配置の高効率なエンジン導入・研究が進んでいた。このような素地から、ヤマハはトヨタ製の量産エンジンを改良して、DOHCヘッドを備えたエンジンを製作することができた。 またヤマハは楽器メーカーが前身で、楽器の材料となる良質木材の取り扱いに長けていたことを活かし、インストルメントパネルとステアリング(ともに前期型はウォールナット、後期型はローズウッド製)の材料供給・加工までも担当した。「開発丸投げ」の俗説 [編集]
2000GTはその成立過程での2社共同開発体制という特異性に加え、実車生産についても、ヤマハおよびその系列企業に委託されたこともあり(後述)、「果たしてトヨタが開発した自動車と捉えるべきか」という疑問が、愛好者、評論家の一部によって呈されている。 自動車関係の書籍・雑誌では古くから、さらに近年では個人によるブログ上などでも(しばしば前後に、自社技術のアピールを目的として2000GTを市販したトヨタへの侮蔑的言辞を伴って)「トヨタは2000GTの自力開発ができず、ヤマハが開発・生産したスポーツカーを買い取っていたに過ぎない」「これは実際には『ヤマハ2000GT』というべきものである」とする辛辣な評、また、「日産・2000GT試作車=トヨタ・2000GTの原型」と断じる極端な説までもがごく一部で流布されている。 このような批評や風説が生じた背景には、トヨタ側単独でのシャーシ開発期間がわずか数か月間ほどで、開発作業期間としてはあまりに短すぎるのではないかという現実的疑問、およびA550XとトヨタGTの開発時期がほぼ前後していて、ヤマハが日産からトヨタへと短期間で提携先を変えたという経緯の不明朗さがあり、自動車マニアや自動車ジャーナリズムが元々抱いていたトヨタの技術水準への疑念[3]と相まって、トヨタへの不信となって表れたものと見られる[4]。 このような経緯から、両社の開発分担が厳密にどのようなものであったのかについてはなお諸説紛々としているが、2000GT開発のプロジェクトリーダがトヨタの河野二郎であったことや、トヨタで行なわれた初期設計およびヤマハ発動機で行なわれた詳細設計にトヨタ側のエンジニアが一貫して参加していた事実を勘案すれば、「開発丸投げ」説は真相を正確に反映しているとは言えず、不適当と処断せざるを得ない。また、ヤマハ発動機は2000GTの開発に中途参加した経緯があり、開発への関与は限定的であったため、開発において主導的な立場をとれるものではなかった。このことから、ヤマハ発動機側は2000GTの開発についての公式な言及を「ヤマハの技術供与」としている。生産・販売 [編集]
生産 [編集]
市販車の本格生産は、ヤマハ発動機に委託された。 鈑金・溶接・車体組立・エンジン組立・塗装の工程は、ヤマハ発動機が静岡県磐田市に新設した3号館工場で手作業によって行われ、FRPパーツ類は新居工場(浜名郡新居町)が製造し、内装パネル関係は日本楽器製造、ボディのプレス関係は1950年代にバイクメーカーとして活躍し、ヤマハの傘下に入った北川自動車工業(後のヤマハ車体工業、1993年4月にヤマハ発動機に吸収合併)の他、(株)畔柳工業といった、トヨタ系試作プレスメーカーも担当した。発売価格 [編集]
当時の2000GTの価格は238万円で、トヨタ自動車の高級車であるクラウンが2台、大衆車のカローラが6台買える程に高価であった。1967年当時の日本における大卒者の初任給がおおむね2万6,000円前後であったから、21世紀初頭における1,500万円から2,000万円程度の感覚にも相当する、一般の人々にとっては想像を絶する超高額車であった。 それでも生産に手間がかかり過ぎてコスト面で引き合わない価格設定であり、全生産期間を通じて常に赤字計上での販売であった。トヨタ自動車にとっては「高価な広告費」とも言うべきものであった。マイナーチェンジ [編集]
市販開始から2年後の1969年8月に、マイナーチェンジが行われた。2000GTは、このマイナーチェンジより前の前期型(1967年5月から1969年7月生産)と、その後の後期型(1969年8月から1970年10月生産)に大別される。2300GT ? [編集]
直列6気筒SOHC 2.253ccエンジンを搭載したモデルも生産されているが市販に至らなかったため正式通称名は発表されておらず不明である。市販された2000ccモデルと区別するため、雑誌やマニアなどが2300GTと称しているが正式名ではない。 現在トヨタ自動車で保有し展示されている(後述)車輌がTOYOTA2000GT輸出仕様となっている事や取り付けられているエンブレムが2000GTとなっている事などから、2000GTと言う名の2300ccモデル、つまり「2000GT」としてDOHC2000ccとSOHC2300ccの2つのモデルでの併売を計画していたとも考えられる。[5] エンジンは当時北米向輸出仕様のクラウンとコロナマークIIに搭載されていた2M型を基本にソレックスツインチョークキャブレターを3連装した2M-B型エンジンを搭載している。型式はMF12Lで、諸説あるがMF12L-100001からMF12L-100009までの計9台の車台番号の物が製作されたとされており、このうちMF12L-100002はトヨタ自動車で保有し東京都江東区のMEGAWEB(メガウェブ)ヒストリーガレージに展示されている、またMF12L-100006はToyota USA Automobile Museumに展示されている。この開発は、ヤマハ発動機がトヨタ自動車に対して提案する形で進められ、アメリカ市場向けの廉価版として本格生産も考えられたようであるが、結局はトヨタ自動車内部での反発に遭い市販には至らなかった。また絶版車雑誌で「アメリカに10台前後存在している」と紹介されたことがある。生産台数 [編集]
赤字生産が続き、イメージリーダーとして十分な役割を果たしたとの判断から、1970年で生産は終了した。 1967年5月から1970年8月までの3年3か月で337台が生産された。| 種類 | 前期型 | 後期型 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 日本向け | 110台 | 108台 | 218台 |
| 日本国外向け | 102台 | ||
| 特殊用途車 | 12台 | 2台 | 14台 |
| 試作・テスト用 | 2台 | ||
| 不明 | 1台 | ||
生産終了後 [編集]
生産終了後、希少価値もあり、2000GTの存在は日本国内外で後年まで伝説的に語られるようになった。熱心な愛好者によるクラブも日本国内外に存在する。日本車における絶版車の人気車種として筆頭に上げられる車種の一つになり、中古車市場では多くの場合プレミアム価格が付いて、良好な状態の2000GTは2000万円を超える価格で取引される事もある。また近年では、新車時に日本国外に輸出された2000GTを日本に逆輸入する例も多数生じている。諸元 [編集]
DOHCエンジン、4輪独立懸架、5段フルシンクロメッシュ・トランスミッション、4輪ディスクブレーキ、ラック・ピニオン式ステアリング、リトラクタブル・ヘッドライトは、トヨタ自動車ではこの車から本格採用された。これらは1980年代以降、量産自動車において珍しくない装備となっているが、1960年代中期においてこれらを全て装備している自動車は、当時としては最上の高性能車と言えた。軽量化のために専用デザインの鋳造マグネシウム製ホイールを用いたことも異例である。ボディ [編集]
当時のスポーツカーデザインの基本にのっとって長いボンネットと短い客室部を低い車高に抑えつつ、全体に流麗な曲線で構成されたデザインは、先行して開発されていたジャガー・Eタイプ(1961年)などの影響を指摘されることもあるが、当時の日本の5ナンバー規格の枠内でコンパクトにまとめられながら、その制約を感じさせない美しいデザインとして評価が高い。ヘッドライトを高さ確保のため小型のリトラクタブルタイプとし、固定式フォグランプをグリルと併せて設置したフロント・ノーズの処理も独特の魅力があった。 このデザインは発表当時トヨタ自動車の社内デザインであるとのみ公表されたが、トヨタ自動車のデザイナーであった野崎喩(のざき さとる)を中心にデザインされたことが21世紀に入ってから明らかにされ、野崎本人によってスケッチやデザイン過程についての談話も公表されている。野崎は2000GTのデザイン以前の1963年に、デザインを学ぶためアメリカのアートセンター・スクールへ留学した経験があり、その当時のスケッチが2000GTのモチーフになったという。 ただし特に日本国外では(ヤマハ発動機が日産自動車とのスポーツカー共同開発を目論んだ経緯から)、それ以前にシルビア(初代)のデザインを監修した[6]とされるドイツ系アメリカ人デザイナー、アルブレヒト・フォン・ゲルツが、2000GTのデザインも手がけたという説が、広く流布している。もっともゲルツ本人は晩年の1996年8月、日本の自動車雑誌『ノスタルジックヒーロー』によるアメリカでのインタビュー(1997年 同誌61号に掲載)で、トヨタ・2000GTへの自身の直接関与を明白に否定している。 ゲルツ・デザイン説の正確な出所は不明だが、日産A550X開発時にゲルツと日産がアドバイザー関係であったこと、および、A550Xもトヨタ・2000GTもリトラクタブルライトのファストバック・クーペという類似性を持ち、後者が前者の改良デザインとも見なせることが風説の原因と見られる。前述の「ヤマハへの開発丸投げ・買い取り」評の存在や、当時のトヨタ自動車に自社で(もしくはさらに広い意味で、「当時の日本人のセンスでは」)このようなデザインを行えるはずがない、という先入観も、ゲルツ・デザイン説が広まる要因となっているようである[7]。 内装はヤマハ製のウッドステアリングとインストルメントパネルをはじめ、回転計などを追加した多眼メーター類や豊富なアクセサリーの装備で、2人の乗員に十分な居住性を確保しながら「高級スポーツカー」らしい演出を図っている。この時代の日本車としては、異例の高級感がある良質な仕上がりであった。ハンドブレーキがダッシュボード下部配置の「ステッキ型」であることが、やや古風な点と言える。ボディーカラー [編集]
ボディーカラーは、前期型では次の3色である。- ペガサスホワイト
- ソーラーレッド
- サンダーシルバーメタリック
- ベラトリックスイエロー
- アトランティスグリーン
- トワイライトターコイズメタリック(ブルーメタリック)
シャーシ・パワーユニット [編集]
古典的スポーツカーらしくボディとは別体となるシャーシは、ジャガー・Eタイプやロータス・エランなどでの先行例に倣ったX型バックボーンフレームで、低重心・高剛性を実現した(2000GTのシャーシが短期間で開発できたのは、これらの著名な先行メーカー製品での手法を巧みに取り込んだという一面も否定できない)。 サスペンションについては、トヨタ車としては初めての本格的な四輪独立懸架となり、前後輪ともコイル支持によるダブル・ウィッシュボーンとして操縦性と乗り心地の両立に成功している[12]。 また、操縦性に配慮してステアリング機構はラック・アンド・ピニオン式とし、高速域からの制動力確保を企図して日本初の4輪ディスクブレーキ仕様とした。 エンジンは、クラウン用として量産されていた当時最新鋭の直列6気筒7ベアリングSOHCエンジンである「M型」(1988cc・105PS)のブロックを流用し、ヤマハの開発したDOHCヘッドに載せ替えるなどして強化した「3M型」を搭載した。このクラスのエンジンとしては小型軽量であり、それゆえ2000GTは、直列6気筒エンジンを使用しながら、現在で言う「フロント・ミッドシップ(エンジンを前車軸と前席の間に搭載する)」レイアウトが可能であった。 3M型は三国工業(現・ミクニ)がライセンス生産したソレックス型ツイン・キャブレターを3連装され、150ps/6600rpm(グロス値)という、当時の日本製乗用車の中でも最強力クラスの性能を得た。これにフル・シンクロメッシュの5速マニュアルトランスミッションを組み合わせた2000GTは、0 – 400m15.9秒の加速力と、最高速度220km/h(最大巡航速度は205km/h)を実現、当時の2リッター・スポーツモデルとしては世界トップレベルに達した。 しかし、ベースが量産型実用エンジンということもあり、ノーマル状態では極限までの高性能は追求せずに、公道用のGTカーとしての実用性をも配慮したチューニングが為されている。このため3M型は、その外見的なスペックの割には低速域から扱いやすいエンジンであったという。前期型と後期型の違い [編集]
前期型と後期型では、次の点が異なる。- フロントマスク部のデザイン変更(フォグランプのリムが小型化され、グリルとの一体感を増し、よりモダンな印象を与えるデザインとなった。)
- フロントウィンカーランプカバーおよびリアサイドリフレクターの形状変更・大型化
- オイルクーラーの冷却用ルーバーパネルが凸型から凹型へ
- インパネ部のデザイン変更
- ステアリングホイールのホーンボタンの形状変更・大型化
- ヘッドレストの追加
- 車内のドアハンドルの形状変更
- カークーラーの追加
- トヨグライド(AT)タイプの追加
- ボディーカラー種類の追加