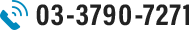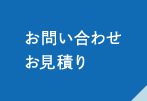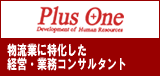令和7年9月度 安全運転教育指導会議
東京都大田区東海4-9-12
IEC構内にて開催

9月の約束
1. 秋の全国交通安全運動を意識しよう!
2025年9月21日(日)~30日(火)を期間として、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。これを機会
として、安全運転の基本を意識し直し、しっかり実践しましょう。
2. 積極的にリスク回避をしよう!
リスク(=危険性)があるにもかかわらず、その回避を図らなければ事故につながります。積極的にリスク
回避を行う姿勢を持ちましょう。
3. 健康増進に取り組もう!
9月は、厚生労働省が推進する健康増進普及月間です。自分自身の健康状態を見直すとともに、
健康増進に取り組みましょう。
秋の全国交通安全運動を意識しよう!
トラックドライバーの重点項目(本誌選択)
〇飲酒運転は絶対にしない
〇漫然運転脇見運転をしない(追突事故防止)
〇交差点での安全確認を徹底する(交差点事故防止)
〇「思いやり・ゆずり合い」の気持ちで運転する
〇ながら運転は絶対にしない
秋の全国交通安全運動期間など
★運動期間:2025年9月21日(日)~30日(火)
★事業用トラックの交通事故ゼロを目指す日:2025年9月30日(火)

健康増進に取り組もう!
●「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ」
●今より「プラス10分」の運動を行う
●毎日「プラス1皿」の野菜を食べる
●1日「7時間以上」の睡眠をとる
●生活習慣病の予防・改善を行う
併せて行う健康管理,
★熱中症対策を継続する
★意識して疲労回復に努める
危険物の種類および危険性・有害性
危険物について正しい知識を持つ
危険物輸送の第一歩は危険物をよく知ること
危険物を輸送する場合、自分が運ぶ危険物の種類・性状、注意事項など正しい知識を
持っていることが求められます。
トラックやタンクローリーで輸送する危険物等には、次の表1に挙げたものがあります。
いずれも取り扱い・ 運転には注意が必要です。危険物の危険性・有害性は、表2のように
分類されます。危険物を輸送する際は、事前に危険物の危険性・有害性について必ず
確認してください。
危険物・毒物の関係法令と種類
危険物 消防法 消防法が規定する第1類から第6類(酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、
引火性液体(ガソリン・アルコールなど)、自己反応性物質(ニトログリセリンなど)、酸化性液体など)
高圧ガス 高圧ガス保安法 液化ガス、酸素ガス・水素ガス・プロパンガスなどの可燃性ガス。
毒性ガスなどで高圧状態にされたもの
火薬 火薬類取締法 火薬、爆薬、火工品(雷管、導火線など)など
毒物・劇物 毒物及び劇物取締法 塩素、ニトロベンゼン、発煙硫酸、黄リンなど
表2:危険性・有害性の類別
危険性 禁水性 水をかけると発火する恐れがあるため、水での消火は厳禁
爆発性 熱、光、摩擦、衝撃で爆発する発火物から遠ざけ距離を
保つことが必要
可燃性など 低温で引火しやすい
有害性 常温 常温で有害ガスを発生する
加熱時・火災時 加熱時・火災時に有害ガスを発生する
水に接触 水に触れると有害ガスを発生する

危険物輸送の基本事項(1)
★危険物などの輸送は、有資格者が乗務する必要がある。
★運行時には、必要な資格の証書等を携行しなければならない。
危険物などの取り扱いには資格が必要
危険物の輸送は、基本的に危険物取り扱いの資格を持った者(運転者または同乗者)が
乗務する必要があります。そして、運行時には、危険物取扱者は危険物取扱者免状を携行
しなければなりません。
また、高圧ガスを輸送する場合は、 高圧ガス移動監視者の資格を持った者が乗務する
必要があります。運行時には、高圧ガス移動監視者は高圧ガス移動監視者講習修了証を
携行しなければなりません。
こうした運行を行うプロドライバーは、法令遵守の精神を持ち、安全運転を行うことはもちろん
危険物についてよく理解し、危険物のリスクを抑える運転・取り扱いを行う必要があります。
危険物や高圧ガスなどを取り扱うことができる有資格者として、準備を怠らず、高い安全意
識を持ち、慎重な運転で運行を完遂してください。
危険物輸送の基本事項(2)
★出庫前に十分な点検と確認を行う。
★運行の際はイエローカードなど必要な備品・携行品を持参する。
★一定量以上の危険物・毒物を運ぶ際にはクルマの前後に標識を表示する。
十分な点検と確認を実施/備品と携行品を持参する(イエローカードなど)
危険物を輸送する際は、出庫前に十分な点検と確認を行うことが重要です。
また、もしもの事態に対処するために備品と携行品(表4を参照のこと)を持参する必要が
あります。
イエローカードは、荷主が発行する、品名別の注意事項等を記載した書面で、台紙が黄色で
あることからイエローカードと呼ばれています。 万が一、事故が発生した場合には、必ず
イエローカードを見て対応してください。
車両の前後に標識を表示する
一定量以上の危険物・毒物を運ぶ際には、危険物輸送を示す標識を車両の前後に表示し
なければなりません。

危険物を運搬する際の基本的な注意点
★安全を確保し慎重に運転する。
危険物積載車両の通行禁止区間
道路法において、危険物積載車両は、基本的に水底トンネルや延長5,000m以上の長大
トンネルなどの通行が禁止されています。ただし、緩和措置などもあるので、危険物を輸送
する際にはあらかじめ確認してください。
通常の運行以上に安全運転に徹することが必要
トラックで危険物を運搬する場合には、安全を十分に確保して慎重に運転を行ってください。
《運行前の注意点》
〇混載禁止の危険物を同一車両に積んではいけません。
〇危険物を運搬する際は、出庫前に十分な点検・確認を行います。
〇必要な車両備品・携行品を持参します。
《一般道走行時の注意点》
〇車間距離を十分にとります。
〇速度は法定速度以内で余裕を持って運転します。
〇“急”のつく運転はしません。安全確認をしっかり行います。
〇交差点は交通が集中する場所なので、特に慎重に運転します。
〇下り坂のカーブでは必ず減速します。その際、エンジンブレーキ、排気ブレーキを有効に
使用します。
〇踏切通過時、しっかり確認し、すやかに通過します。
《高速道路走行時の注意点》
〇スピードを抑制して運転します。
〇必要十分な車間距離をとります。
〇雨の日は、特に前述2点を意識ます。
《積み降ろし時の注意点》
〇指定された位置に車両を停めて輪止めをします。
〇火気、火花は厳禁です。また、静気発生防止をします。
〇車両から離れず、荷受けを行うの危険物取扱者と相互に積み降ろを確認します。
万が一の事故発生時にも適切な対応を!
★あわてずに必要な措置を適切に実施する。
①事故発生時の応急措置
ハザードランプと停止表示板(三角表示板)などで事故を知らせます。事故発生を大声で告げ
風上などの安全な場所に人を移動させます。付近の可燃物を遠ざけます。
②緊急通報
消防・警察に事故発生の通報を行います。(いつ、どこで、 なにが、どうした、けが人の有無、
自分の名前など)
③緊急連絡
会社と荷主に連絡し、事態・ 状況をはっきりと伝えます。
④漏洩・飛散
危険性の有無を確認し、可能であれば漏洩を止める措置をとります。
(イエローカードの記載に従う)
⑤周辺火災
危険性の有無を確認し、近隣住民の避難を優先させるか、消火を行うかを判断します。
⑥引火・発火
もし引火・発火した場合は、 消防・警察に通報し、近隣住民を避難させます。
⑦救急措置
安全な場所へ移動し、「皮膚や目への付着」「吸入していないか」を確認します。
(イエローカードの災害拡大防止措置に記載された内容に従って応急手当を行います)

タンクローリーの車両特性
★重心が高い、荷の液体が動くことで重心が動く。
タンクローリーの車両特性を踏まえ慎重に運転すべき
タンクローリーは、車両の重心が高いことに加え、石油類などの液体を積載していることから
事故リスクにつながる車両特性を有しています。タンクローリーを運転するドライバーは、
次に挙げる車両特性を踏まえ、十分に注意して慎重に運転する必要があります。
《タンクローリーの注意すべき車両特性》
〇通常においても、重心が高いことにより横転の危険性が大きい車両です。
〇走行中にタンク内で液体が動くことによって、さらに横転リスクが増えます。
〇カーブや交差点で急旋回するときには、遠心力で積荷の液体が外側に片寄ります。
〇急ブレーキや急発進など、“急”のつく運転をすると、前または後ろに積荷が片寄ります。
〇トレーラタイプの場合には、ジャックナイフ現象など、特有の現象を生じやすい車両特性が
あります。
タンクローリーの運行上の注意事項
★積荷が有するリスクを意識し、危険の抑制に努める。
人ごみを避ける、火気を避けるなどの注意が必要
タンクローリーは、石油類などをはじめとした危険物や高圧ガスなどを積載して運ぶ場合が
多くあります。そうしたタンクローリーを運転するドライバーは、積荷が有するリスクを意識し、
危険を抑制するように心がけ、行動することが求められます。
≪運行中の注意事項》
〇高圧ガスなどの輸送の場合には、 ガスの温度を常に40℃以下に保ち、 ガスの温度の
上昇を防ぐため、水をかけたり、日陰に停めるなどの対応が必要です。
〇繁華街や人ごみは避けて通行します。
〇上方の障害物には注意が必要です。車両の高さよりもタンクの高さが高い場合には、高
さ検知棒を設置しましょう。
《駐車時の注意事項》
〇人の集まる施設、文化財等の重要な施設、住宅密集地に近い場所での駐車は避けます。
〇交通の流れが連続していなくて、 火気のない広い場所に駐車します。
〇駐車中には、やむを得ない場合を除いてドライバーは車両から離れないことが必要です。
やむを得ず離れる場合にも、監視できる場所にいるようにします。
baibaikin