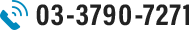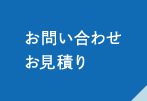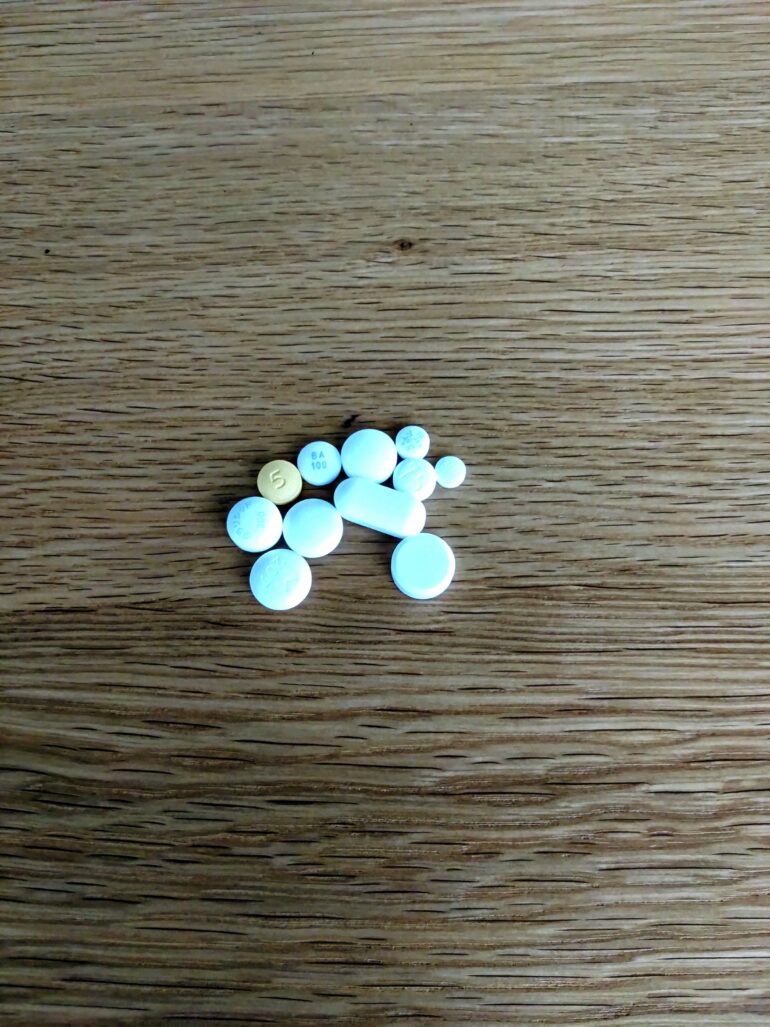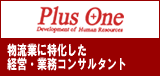毎度、中山さんです。
百日咳と肋骨骨折中(>_<)
先日、ゴルフ。

フェアウエイが大変な事になってる。

しかもドライバーの落下地点あたりが酷い事になってる。

猪の仕業です。

私は、満ブリ出来ないのでどうなるか不安だったけど

飛ばない代わりに真っ直ぐ行く(^◇^)

終わってみたら、いつもと変わらない( 一一)
だた、流石に肋骨がつくまでは当分お休みだな。
baibaikin

毎度、中山さんです。
百日咳と肋骨骨折中(>_<)
先日の事、本家の法事。
鎌倉霊園。

変な話、こんな事でもないと親戚一同集まることもないので・・・

せっかく美味しい料理が出て来ても、味がわからない。
しかも車なので酒も飲めない。
おまけに、皆と話すのに夢中で料理の写真も撮り忘れた。
ただ、親戚 中山家グループLINEに新しい親戚が追加された(^◇^)
baibaikin
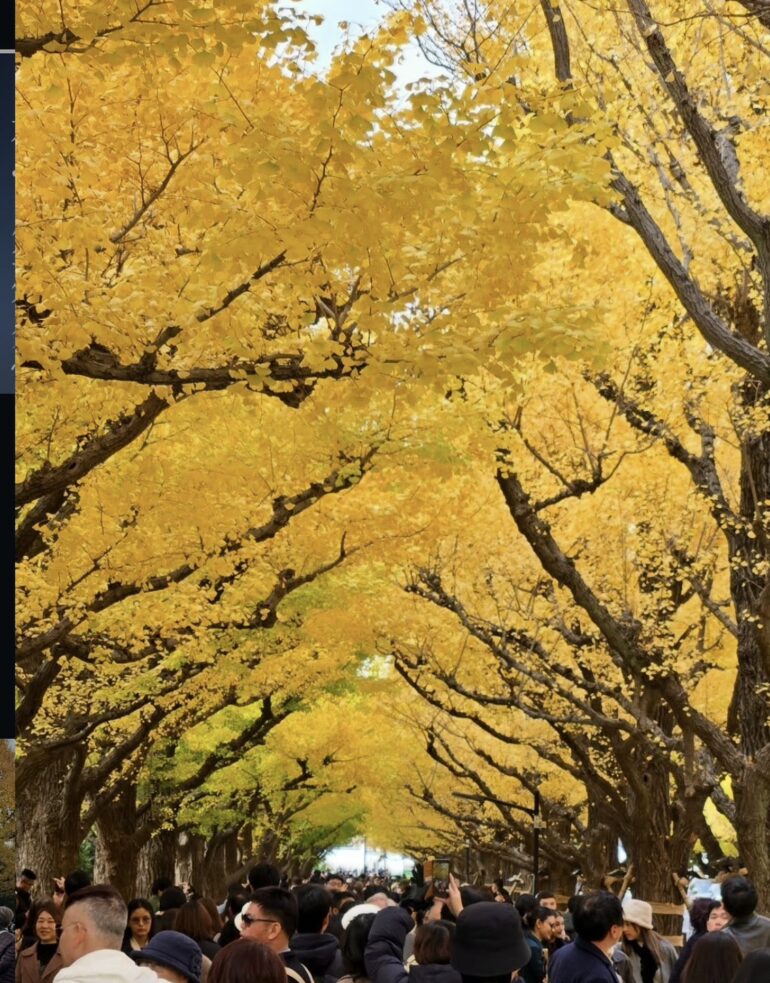
毎度、中山さんです。
百日咳と肋骨骨折継続中( 一一)
お友達から写真が送られてきました。
黄色く色づいて綺麗だけど人がすごいね。

今夜は秋刀魚。
今年は少し安く手に入るね。
でも、残念ながら味がよくわからない・・・
早く薬、卒業したい。
これから忘年会シーズン突入だと言うのに!
baibaikin

毎度、中山さんです。
以前、百日咳と肋骨骨折継続中(>_<)
先日、次長と課長が吉野家で食べて美味かったと言う『牛すき鍋膳』を、
買いに行くという事で私の分も一緒にお願いした。
が、これは店舗で食べた方がいいかもですね。
今朝の事、咳をした時に『ボキ!』と・・・
これで二本目が骨折となりました。
baibaikin

毎度、中山さんです。
先日の朝食。
いつものTKG。
ただ、大好きなTKGも毎日食べてると流石に飽きて来るので味変。
今回は、七味唐辛子とおろしニンニク(^^♪
匂いは気になるが毎日マスクしてるから問題なしかな(^◇^)
正直、これでも味わからない。
薬の副作用って怖いですね。
ちなみに、服用を終えたら元に戻るらしい。
baibaikin

毎度、中山さんです。
先日のランチタイム。
お蕎麦が売り切れだったのでカツ丼です。
しかしながら、現在咳が収まらないので、
強い咳止めを処方されています。
副作用としては、味覚障害。
何食べても味がわかない・・・

飛び石食らって、フロントガラス交換です。
綺麗になりました。
物価高騰、色々な物が値上がりしてますが、
ガラスも、びっくりする位に高くなってました。
車間距離必須、硝子高い!
baibaikin

毎度、中山さんです。
先日、11月22日。
『いい夫婦の日』土曜日だったので、
丸ビルの高級フレンチを予約。
ギリギリまで行く気でいたが、さすがに咳が酷く周りに迷惑をかけると思い断念。
寂しく家で焼鳥。
baibaikin

毎度、中山さんです。
先日のこと。
相方さんが実家に行って遅くなるとの事。
久しぶりに、すき家(^^♪
身体は少しは良くなって来ていたはずが、
朝の咳で肋骨いった!
baibaikin